こんばんは。火曜日担当の中嶋です。
身内の話で恐縮ですが、
読書好きの娘が夏目漱石の
「坊っちゃん」を読んでいました。
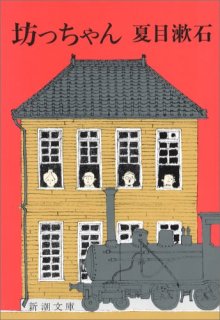
私も懐かしく、娘から取り上げるように読破。
娘が自分と同じ本を読む年になったのも感慨深いですが
それよりも何よりも、
「だから清の墓は小日向の養源寺にある。」
この最後の一文にしびれています![]()
今も思い出しながらしびれています。
この読後感に共感された方とお話をしたいです。
----------------
さてそんな坊ちゃんを読んでいて驚いたのが
小説中に「風船」が出てくること。しかも、単に
ふくらませるのではなく、プカプカと浮いてどこかに飛んでいくのです・・・
漱石はほぼ明治時代をまたがるように生きた人ですから
もう100年も前に風船が空を飛んでいたのだと感慨深い。
ヘリウムで浮かせていたのかな?それとも、当時はより手に入りやすい
水素だったのでしょうか?
小説も年を経て読むと違う場所で感じたりするんですね。
というわけでちょっと調べてみました。
1897年頃、日本でドイツ製ゴム風船が流行とあります。
[出展:Wikipedea]
坊ちゃんの発刊が1906年ですから、辻褄があいました。
----------------
本日は、デイジーさんのスクールが開催。
3月の講座が震災の影響で中止となり、
皆様2ヶ月ぶりの再会。
このような教室を開かれることの幸せを
皆様かみしめるような、温かい雰囲気の素晴らしい教室でした。
さて、その作品です。

毎回その立派さに
惚れ惚れします。
申し訳ありませんが、次回は空きが出ませんでした。
人気講座ゆえ、申し訳ございません。
もし、ナランハ、そして私中嶋に
何とかしてくれというご希望がございましたら
ぜひドシドシお寄せください。
皆様のお声が状況を動かします。
それでは、また来週!
----------------

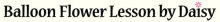


 コメント
コメント
